STUDENT LIFE 学生生活
令和7年度
学生と学長の意見交換会
6月12日(木)17:00〜18:30
| 出席者 | 学生:学生自治会執行部9名 | 教員:学長・副学長ほか計5名 | 事務局:4名 |
|---|
川崎市立看護大学では、よりよい大学を作り上げていくことを目的に、学生からの意見を聴取し教職員とディスカッションする「学生と学長の意見交換会」を毎年実施しています。2025年6月12日、今回で4回目となる同会が開催されました。

「学生と学長の意見交換会」は、大学の施設・設備や学生支援について、学生を代表する学生自治会執行部と大学の教職員が意見を交換する場です。学生のみで構成する学生自治会(役員は1年生〜4年生が就任)は、年に一度、事前に各学年の役員が学年ごとに大学への要望を調査し、内容をとりまとめます。要望については、具体的な意見を交わすため、対面による「学生と学長の意見交換会」を催し教職員は、各要望に対し回答・改善策を提示・実行します。
開会にあたり、坂元昇学長が挨拶に立ち、「学生と学長の意見交換会」は自分が出席する様々な会議の中でも最重要会議の一つであると心得ていること、学生たちには忌憚なく思う存分に意見を述べてほしいと率直に語りかけました。
続いて、今年度の学生自治会長が挨拶し、学生の意見を直接学長に伝えられる機会があること、自分たちの声が大学の運営に反映されていることへの感謝を述べました。
司会進行は佐藤文教授が務め、継続的課題に関すること、キャンパスライフの向上に関すること、授業・成績に関すること、学生支援に関することなど、1時間半にわたり真剣に意見が交わされました。
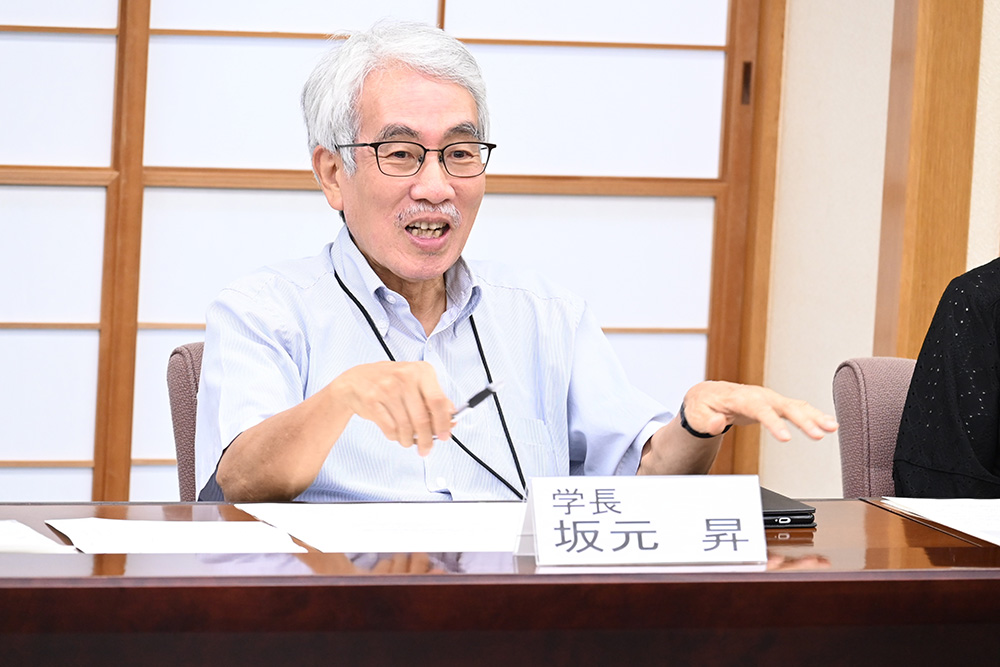

継続的課題に関する議題の中心は、かねて学生側が要望していた「学食の復活」で、大学側からは今年度後期の復活に向けて調整中である旨の回答がありました。学長からは「メニューなどに学生の意見も取り入れたらどうか」との意見があり、学生自治会と、実現に向けた前向きな協議が進められました。
施設・学習環境の議題の一つであるWi-Fi環境については、学生側が、授業の出席入力の際にアクセスが集中してWi-Fiがつながりにくい状況を説明し、以前から改善を求めていました。大学側は、新たな中継器の設置を検討しつつ、中継器増設にかかる費用の高騰に理解を求め、つながりにくいエリアの状況改善に向けて事業者と協議する考えを示しました。
キャンパスライフの向上に関するゴミ箱の問題では、学生側の「ゴミ箱のゴミが溢れ出しているので改善してほしい」との要望が議題となりました。大学側は、容量の大きいゴミ箱を設置し直す方針を示しましたが、学生同士でゴミの分別やマナーに対して声を掛け合うこともゴミの減量化につながるという意見が生まれ、双方が支持する場面がありました。学生を思う大学の提案と学生自らの気づきが交換されることで、建設的な意見交換が展開されました。
その他、授業・成績に関すること、学生支援に関することなど、解決に至った議題と継続的に検討していく議題について、真摯な意見が交わされました。
学生たちへの、要望の改善の進行状況は、前期(4月)後期(9月)のガイダンスで報告されるほか、3月に年度のお知らせとして掲示板にも掲載されます。


学生自治会の感想
私たちの要望は十分伝えられましたし、真剣に受け取っていただけたと感じました。学食復活は実りのあったテーマの一つで、後期にはまた学食を利用できそうで安心しました。この意見交換会は、大学に求めるだけの一方的なものではなく、私たちも努力することでスピーディに改善が進む場合があります。我慢するしかないと不満を抱くより、意見を言える機会を活用し、自分たちの学びを良くするための、様々な議題について協議でき、とても有意義な会でした。
「学生と学長の意見交換会」について学長にうかがいました
- 質問:
- この意見交換会の目的と意義を教えてください。
- 学長:
- 学生から意見を聴取し、教職員とディスカッションすることにより、より良い大学をつくり上げていくことを目的としています。学校教育法第109条第2項に規定される「大学評価基準」に基づく、「国・公・私立大学の教育研究活動等の総合的な状況に関する評価」に向けた取組の一つです。
(「大学評価基準」のうちの「施設及び設備並びに学生支援に関する基準」に対応するもの)
- 質問:
- 学生の声は、学長の意思決定にどのように反映されていますか。
- 学長:
- 学生からの意見、提案等は真摯に受けとめ、必要性や優先度合いを勘案しながら対応していきます。学長自らが参加し、直接答えていますから、実現に向けた努力は惜しみません。ただし、大きな予算が必要になる件は学長の判断だけでは難しく、そこはご理解いただきたいと思います。
- 質問:
- これまでに印象に残った提案はどんなものでしたか。
- 学長:
- 学食への要望について、学生が全国の大学のデータをとりまとめ、そのうえで発言していたのは実に立派だと思いました。一方で、事務の対応の不十分さに関する意見があったことは心が痛かったです。
- 質問:
- 意見交換会は今回で4回目です。学生が大学運営に積極的に関わることは、学生や大学にどのような変化をもたらすとお考えですか。
- 学長:
- 学生は、大学運営に積極的に関わることで、組織運営の視点やコミュニケーション能力、問題解決能力などの実践的なスキルを身につけることができます。自らの意見やアイデアを反映させる機会は、主体性や責任感、リーダーシップや協働性の向上にもつながります。これらの経験は、将来の看護実践の土台になるでしょう。また、大学側としては、学生の意見によって設備等の改善点が明らかになり、より良い学習環境の整備につながるほか、大学側と学生側の相互理解と信頼関係が強化され、結果として学生満足度や学習効果も向上すると考えています。対話を通して一緒に考え変えていく、ある意味民主主義の本質を学べる機会でもあります。
- 質問:
- 学生への期待など、メッセージをお願いします。
- 学長:
- 最終的に川崎市に予算要求をするのは学長ですが、学生も、予算の決まる市議会の仕組みや、川崎市全体の予算について関心を持ってください。川崎市は地方交付税の不交付団体なので、国からの補助金はありません。つまり、他の国公立大学とは異なり、本学の低額な授業料や学内設備は、全額を川崎市民や市内企業等からの税金で賄われているのだと認識してほしいです。また、日々の勉学を通して自己実現を模索する中で、どんな些細なことでも、社会に何が貢献できるかを考えてほしいと思います。ただ同時に、勉強だけでなく学生時代を思う存分楽しむこと、友人を作ることも、自己実現のために欠かせないのは言うまでもありません。
学生と教職員が手を取り合って前進する大学として
私にとって「学生と学長の意見交換会」は、学生たちの本質を突く問いや私たちが持っていない視点に驚かされる、他の会議とは全く違う緊張感と楽しみな気持ちがせめぎ合う会議です。学長として、直に学生たちと向き合う機会は貴重で、学生と大学が手を取り合ってより良い大学を作り上げていくという共通の目標に励まされます。今年も、学生たちの本音や教職員の日頃の考えが活発に表明され、うれしく思うとともに、学生の要望に応えていかなければと、思いを新たにしました。
学長 坂元 昇

